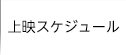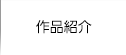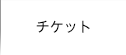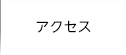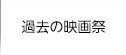有機農業や環境、農薬、遺伝子組み換えを主なテーマに内外の秀作を上映してきた国際有機農業映画祭は18回目を迎えました。今年も武蔵大学を会場に開催します。今回は「森・水・土の声を聴け」をテーマに、日本で制作された5作品を上映します
2012年、私たちは『お米が食べられなくなる日』を上映しました。そして12年後、《10年後には、日本で米づくりができなくなるかもしれない》という懸念が現実化したのが今年の夏でした。スーパーの棚から米がなくなる「令和の米不足」です。1970年に始まった減反政策による政策災害ともいえるでしょう。そして、農民の平均年齢は70歳に届こうとしています。生産費を超えることのない米価による赤字でも作付けを続けてきた農家も限界に達し、離農が増えています。今では40歳でも若手と言われています。20年後にはどのような状況になっているでしょうか。日本の主食である《米》が、《本当に食べられなくなる日》が現実化しつつあります。こうした状況に、もう一度『お米が食べられなくなる日』(2012年/日本/35分)を上映し、米を作っている若手農家の声を聴く「【野良語り】百姓の声を聴く」を行います。
この数年、「永遠の化学物質」と言われる有機フッ素化合物(PFAS)の問題が焦点化してきています。米軍基地が原因の沖縄や化学工場による大阪市や静岡市、野積みされた産業廃棄物による岡山県吉備中央町など各地の水道水のPFAS汚染が明らかになってきました。こうしたPFAS汚染について沖縄テレビ制作の『続・水どぅ宝 PFAS汚染と闘う! Fight For Life』(2024年/日本/47分)に考えたいと思います。植田武智さん(科学ジャーナリスト)に各地の状況とともに解説していただきます。
日本の森林率は約7割。二酸化炭素を吸収し、水を貯め、土を作り、有機物を供給する森を守っている人たちに焦点を当てた『サステナ・フォレスト 森の国の守り人(もりびと)たち』(2024年/日本/69分)で森と循環を考えます。
森の中で動物のうんこやその死体、朽ちた木々や葉っぱは、小さな虫やキノコが次の世代の糧となる有機物に分解しています。『うんこと死体の復権』(2024年/日本/106分)で循環を阻害するヒトと自然の循環を考えます。
循環の入り口でもある《食べること》を、食育菜園の創始者であるアリス・ウォータースを描いた『食べることは生きること アリス・ウォータースのおいしい革命』(2024年/日本/66分)で考えます。解説は『食育菜園 エディブル・スクールヤード』(2006年)の訳者でもあり、その実践者でもある堀口博子さん(エディプル・スクールヤード・ジャパン代表理事)です。