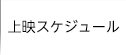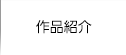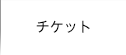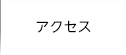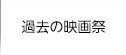有機農業や自然環境などに関心をもち、取り組んでいる個人が集まり、運営委員会を構成して活動している非営利の市民グループです。今回を含め延べ141作品を上映しました。日本初公開作品45作品のうち37作品の字幕制作を自前で行いました。
2006年、遺伝子組み換えを多面的に追ったドキュメンタリー映画『食の未来』(原題〝Future of Food”)の日本語吹替版制作を担った人々が、有機農業をテーマとした映画祭の開催を呼びかけました。この呼びかけに、有機農家、有機農業団体関係者、反農薬運動関係者、ジャーナリスト、編集者、学生などが集まり、開催に向けて運営委員会を作りました。日本という枠にこだわることなく広く海外作品も上映しようと「国際有機農業映画祭」と名付けました。
2007年11月に第1回となる国際有機農業映画祭2007を開催して以降、毎年秋に開催してきました。農作業が一段落した秋に開催することで、多くの農家や農業関係者に参加して欲しいという 期待をこめて開催時期を農閑期としています。毎年、多くの有機農家や、有機農家で研修している若い人たちが参加しています。(コロナ禍最中の第14回と第15回は配信により開催しました。)国際有機農業映画祭は単に有機農業や食の安全といった問題のみにとどまらず、自然と人との関係の在り方や、それを支える価値観、社会のつくり方といったところまで視野を広げ、“思想として の有機農業“を考える構成をめざしています。国際有機農業映画祭の活動がきっかけとなって、国内でも各地で同様の映画祭が開催されるなど、上映活動の輪は大きく広がっています。また、上映作品も国内だけでなくアジア、アフリカ、中東、ヨーロッパ、南北アメリカにまで目を広げ、運営委員会で翻訳と字幕の制作を手掛けるなどの努力を積み重ねてきました。上映した作品の一部は貸出しも行っています。
東日本震災と福島原発事故があった 2011 年、福島第一原発事故直後から取材し、原発を生みだした現代社会の矛盾を有機農業という営みをもとに考える自主製作映画『それでも種をまく』を制作。英語、中国語、タイ語、ベトナム語、ドイツ語、フランス語、スウェーデン語の字幕版を制作し、ウェブで公開しました。2019 年には、8 年後の福島の有機農家のその後を追った『それでも種をまく 2019』を制作し、その年の国際有機農業映画祭 2019 で上映しました。
3.11から10年を経、その後の様子は決して良い方向に行っているとは言えません。SDGsとして17項目について、地球規模での改善取組みが示されています。上映作品も、1国の問題に終わらず、世界がつながっていることを描いたものが多くなりました。一緒に考える機会の一つになる映画祭になっていると言えるのではないでしょうか。
国際有機農業映画祭が、単に有機農業や食の安全といった問題にとどまらず、自然と人との関係の在り方やそれを支える価値観、社会のつくり方といったところまで視野を広げ、”思想としての有機農業“を考える構成をめざす当初の形になり、動きにつながっていると感じます。
2021年と2022年は、続けて、コロナ禍による実会場での上映会は実施できず、これまでの1日中の映画祭を、初めて、オンラインのみの上映会として、取り組みました。オンライン上映により、これまで都内での開催のため、参加が叶わなかった遠方の方々もオンラインで参加くださり、とても身近な映画祭に感じたとの感想をいただきました。4月~3月を年度とする取り組みでは、2022年度となる2023年3月18日、第16回映画祭を3年ぶりの実会場で実施することができました。国際有機農業映画祭2023,2024は、武蔵大学を会場に盛況のうちに終了することができました。
第19回目となる国際有機農業映画祭2026は、日比谷図書文化館日比谷コンベンションホールにて開催いたします。どうぞ、ご参加下さいますよう、ご案内いたします。